|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ランチョンセミナー
|
ジルコニアを用いたメタルフリー修復を成功に導くためのベーシックと新潮流 竹市卓郎愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座 生体親和性の高いメタルフリー修復に対する患者の要求が高まるにつれて、高強度セラミックスをフレームワーク材料として用いるケースが増加し、その重要性が高まっています。近年、高強度セラミックスである酸化ジルコニウム(ジルコニア)と歯科用⊂AD/CAMシステムを用いることによってメタルフリーによるオールセラミック修復の適応が拡大しました。また急速に普及しているフルカントゥアージルコニア修復lま、従来と比較して高い審美性も有するようになりました。今回のセミナーではジルコニアを用いた修復法の利点、欠点、臨床ステップでの細かな注意点、さらに最新の臨床成績について解説します。みなさまの明日からのジルコニアを用いたメタルフリー修復に役立つセミナーになれば幸いと考えています。
|
|
特別講演
|
歯科接着の発展 これまで、これから 千田 彰愛知学院大学歯学部保存修復学講座 歯科接着は、1955年にBuoncore MGが80%リン酸でエナメル質をエッチングし、MMAレジンをエナメル質に接着させたことに遡る。その後接着システムは、エナメルエッチングによるレジン・エナメル接着を第一世代とし、現在は第七あるいは第八世代となる多目的の1ステップシステムヘと発展してきた。この歯科接着の発展は、単に歯冠修復物の支台歯や窩洞など歯質側への個着力」と「耐久性」に貢献したのみでなく、修復物と歯質との間の辺緑漏洩を防ぎ、何といっても、機械的勘合力に頼る従来の歯冠修復法に必要な多圭の歯質削除量を大幅に減じ、2000年のFDl委員会による「Minimal Intervention Dentistry」提言の根拠の一つとなり、21世紀に向けた新たな歯科医療のあり方を示す基盤をもたらした。 歯冠修復法には、Blackの原則にある機械的な勘合を基本とした修復物保持の考え方が、長く利用されてきている。確かに、これらの原則に従うのであれば、修復物の歯質への固着、維持に歯科接着は不要であり、機械的な勘合力(摩擦力)を増す意味でのセメントがあれば良い。したがって多くの臨床家は、このセメントの物理、機械、生物的な性質(性能)については関心をもつ。一方歯科接着は、レジン接着であり、レジンを用いた直接法修復に利用されるものという概念が形成されてしまい、各種のクラウンなどの大型間接法歯冠修復への歯科接着の展開は遅れたといえる。事実金属冠、セラモメタル冠などへのレジン接着については歯質への接着と異なり有効なものが開発できなかったことも間接法への歯科接着の応用が遅れた原因となったといえよう。 しかし1983年のボーセレンラミネートペニアの紹介は、上述の間接法へのレジン接着の遅れを一気に取り戻し、レジン接着による歯質保存とセラミックスの融合による「真の審美修復」をもたらし、間接法へのレジン接着の展開の必要性を歯科臨床に認識させるものとなった。レジン接着そのものは3ステップ、2ステップシステムと進化し、現在は1ステップとなったうえ、この間接法修復への展開も考慮した「多自的」システムとなり、最近の各種オールセラミックス、CAD/CAM歯冠修復物にも対応するものとなっている。 本講演では、「メタルフリー」のための接着について皆さんと議論し、間接法修復における「セメント」と「接着」の基本的な相違をお話し、臨床家の皆さんのMIと高品質な審美的歯冠修復実現のお役に立てるよう努めたい。 
|
|
一般講演
|
歯科用インプラントによつて引き起こされる金属アレルギーとチタンアレルギーのリスクについて○細木真紀、松香芳三徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能校合再建学分野 チタンは耐食性にすそれ、生体親和性が高く、アレルギー反応を惹起することが少ない金属材料として日用品や工業用品はもとより、整形外科用の固定プレートや歯科用インプラントなどの用途に広く用いられている。しかし、最近になってチタンを原因とするアレルギーが疑われる症例が医科・歯科から報告されてきている。我々が担当している歯科用金属アレルギー外来では2002年よリチタン試薬をパッチテストに取り入れているが、チタンアレルギーが疑われる症例は増加する傾向にある。 そこで本発表では歯科用金属アレルギー外来で行った疫学調査結果を報告するとともに、当科でチタンアレルギーが疑われた患者のうち特徴的な症例を供覧する。本発表を通して、チタンアレルギーの実態・危険性、歯科用インプラントと金属アレルギーの関連性を報告する。 II.方法 被験者は、2010年4月から2014年3月の間に徳島大学病院歯科部門・歯科用金属アレルギー外来を受診した患者270名(男性61名,女性209名,平均年齢53.9歳)である。 パッチテストは鳥居薬品社製/でッチテスト試薬金属、チタン試薬を含む自家製剤、合計21元素26品目で行った。Jマッチテスト用絆創書パッチテスタートリイを用いて患者の背中に貼付した。皮虎反応の判定はlnternational Contact Dermatitis Research Group 基準に法って判定し1)、埴ら2)の方法に従って総合判定した。 Ⅲ.結果 270名中217名(80.4%)が何らかの金属に陽性反応を示した。水銀(34.6%)、パラジウム(34.2%)、クロム(33.1%)、ニッケル(31.6%)は他の金属と比較して高い陽性率を示した。チタンに関しては17名(6.3%)が陽性であった。 また、270名中16名(5.9%)が歯科用インプラント治療後に何らかのアレルギーを疑わせる症状を訴えて受診した患者であった。このうち11名は何らかの金属に陽性反応を示し、4名(1.5%)はチタンに陽性反応を示した。歯科用インプラント治療後の患者群とインプラント治療を受けていない患者群のチタン試薬(0.1% TiCl4)に対する陽性率を比較すると、歯科用インプラント治療後の患者群(陽性率25%)は、インプラント治療を受けていない患者群(陽性率4.7%)に比較して有意にアレルギー陽性率が高かった。 Ⅳ.考察 今回の調査において何らかの金属に陽性反応を示した患者の割合が80.4%と高かったのは本患者群の96.3%が歯科あるいは医科から金属アレルギーの疑いにより紹介された患者であったためと考えられる。 チタンアレルギーについては更なる経年的な調査が必要であるが、日常品へのチタン材料の使用頻度が高くなリチタンに暴産される機会が増加しているため、今後チタン陽性患者が増加する可能性は高いと考えている。また歯科用インプラント治療後の患者群でチタンに陽性反応を示した割合が高かったことより、歯科用インプラントを原因としたチタンへの感作の可能性が疑われた。 今後はどのような患者においてチタン材料がアレルギー症状を引き起こすリスクが高いのかついて検討していく必要がある。 Ⅴ.文献 1)Lachapelle J-M, Maibach Hl.Patch Testing and Prick Testing:A Practical Guide Official Publication of lCDRG.2nd ed,. Berln Springer;2009. 2)埴英朗、井上昌幸感作陽性率について井上昌幸、中山秀夫 歯科と金属アレルギー 東京:デンタルダイヤモンド、1993.54-69 CAD/CAM冠およぴFMCにおける臨床的調査○原田亮、土屋淳弘、尾関創、阿部俊之、佐久間重光、橋本和佳、伊藤裕、服部正巳*愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座, *愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 Ⅰ.目的 平成26年4月1日より、CAD/CAMシステムにより作製されたハイブリッドレジン製のクラウン(以下CAD/CAM冠と記載)が保険導入された。これまでに筆者らは、開業歯科医に対しCAD/CAM冠の利用の有無についてアンケートを行った1)。その結果、CAD/CAM冠を利用していない理由として、適合不良、脱離および破折に対する不安などの意見が多くみられた。今回筆者らは、技工所に保管されたデータより、患者の口腔内に試適、装着されたCAD/CAM冠およぴの保険適応の全部金属冠(以下FMCと記載)の再製率を比較し、検討した。また、CAD/CAM冠における再製理由についても調査したので報告する。 Ⅱ.方法 調査対象は、愛知県の某技工所(以下技工所Aと記載)、岐阜県の某技工所(以下技工所Bと記載)で、技工所Aでは平成26年6月1日から平成27年12月31日までに、技工所Bでは平成26年1月1日から平成26年12月31日までに作製された上下顎両側第一、第ニ小臼歯のCAD/CAM冠およびFMCとした。調査方法は、両技工所に対するアンケート方式で行った。 Ⅲ.結果と考察 各技工所におけるCAD/CAM冠およぴFMCの再製率の比較には、X2検定を用いた。(P<0.05)技工所Aでは、CAD/CAM冠は総件数11103件、再製件数344件、総件数に占める再製率は3.1%で、FM⊂は総件数9691件、再製件数310件、総件数に占める再製率は3.2%であり、両クラウンの再製率に差は認められなかった。技工所Bでは、CAD/CAM冠は総件数8423件、再製件数307件、総件数に占める再製率は3.6%で、FMCは総件数6059件、再製件数294件、総件数に占める再製率は4.9%であり、CAD/CAM冠はFMCよりも再製率が有意に低い結果となった。またCAD/CAM冠における再製の理由の内訳は、技工所Aでは、不適合が44.9%、破折およぴl裂が32.3%、隣接面接触関係の不良が5.5%、その他は17.3%であり、技工所Bでlま、脱難が67.2%、破折および亀裂が24.6%、隣接面接触関係の不良および不適合が8.2%であった。今回の結果から、CAD/CAM冠の再製率はFMCと比較し、同等もしくはそれ未満であることがわかった。 Ⅳ.文献 1)竹内慶子、阿部俊之、原田亮ほかCAD/CAM冠に関する臨床的調査第一報再製率について 日本デジタル歯科学会誌2015;5:186 ハイブリッドレジンと接着性レジンセメントによる接着強さの比較○土屋淳弘、阿部俊之、橋本和佳、佐久間重光、尾関創、原田亮、池田大意、伊藤裕、服部正巳*愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座.*愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 保険適用のハイプリツトレジンブロックおよび接着性レジンセメントには様々な種類が存在する中、当講座では第33匡旧本接着歯学会、第6回日本デジタル歯科学会において各種ハイプリツトレジンブロックと各種接着性レジンセメントの接着強さについて報告した。 本研究では、さらに新しく市販された接着性レジンセメントとの接着強さについて追加検討した。 II.方法 ハイブリッドレジンブロックには、セラスマート(ジーシー)、松風ブロックHC(松風)を使用した。ブロックは常温重合レジン・ユニファストトラッド(ジーシー)で包埋し、ブロック表面を耐水性シリコンカーバイドペーパー#600にて研磨した。その後、50JJm酸化アルミナによるサンドブラスト処理およぴスチームクリーナでの清掃を行った。 被着体はユニフィルコアEM(ジーシー)を使用した。接着性レジンセメントには、バナビアV5(クラレノリタケ)、ジーセムリンクフォース(ジーシー)、ブロックHCセム(松風)を使用した。被着面は、厚さ50〃m直径6mmの穴あきシールを貼付し規定した。各セメントに対して試料は5個ずつ作製した。接着強さは、引っ張り圧縮試験機(インストロン社製)を用い勇断試験により検討した。それぞれのブロックとレジンセメントの接着強さの検討には一元配置分散分析法を用い、有意差が認められた場合には多重比較(Tukey)を行った。有意水準は5%未満とした。 Ⅲ.結果と考察 最も大きな接着強さを示したのは、セラスマートではジーセムリンクフォースを使用した19.49±3.82Mpaであり、その破断面は凝集破壊を呈していた。また松風ブロックHCでも最も大きな接着強さを示したのは、ジーセムリンクフォースを使用した18.78±3.66Mpaであり、その破断面は凝集破壊であった。 今回の結果より、接着性モノマーの違い、その他成分の化学的結合の差、操作ステップの数など様々な因子が接着強さに起因していると考えられた。 Ⅳ.文献 1)土屋芳弘、阿部俊之、橋本和佳ほか 新規保険導入されたハイブリッドレジンとコア用レジンとの接着強さ第4報 各種接着性レジンセメントによる接着強さの比較 日本デジタル歯科学会誌2016;6:112 低温劣化によるジルコニアの透光性の変化○鈴木崇由、加藤大輔、伴清治*、河合達志*、村上弘、服部正巳愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座.*愛知学院大学歯学部歯科理工学講座 ジルコニアは機械的強度に優れるが、透光性は歯科臨床的には不十分であるとされている。したがって、ジルコニアを使用した修復物表面は、通常長石系陶材により被覆されている。近年、透光性を改善したジルコニアが開発され、これらの高遠光性ジルコニアの使用により、ジルコニアのみの「フルカントゥア」といわれる事実修復物が汎用されている。この修復物はジルコニアが直接口腔内に露出するため、表面の劣化が懸念されている。本研究ではオートクレーブ装置を用いて加速劣化試験を行い、ジルコニアの透光性の変化について検討したので報告する。 Ⅱ.方法 試料として高透光性ジルコニアを4種(Cercon ht、ZENOSTAR pure、inCoris TZl、Katana HT)、従来型を3種(Cercon、ZENO Zr、inCoris ZI)の計7種の市販歯科用ジルコニアを用いた。ジルコニアは直径20mm、厚さ1.Ommの円盤を焼結前のブロックからダイヤモンド刃カッティング装置により切り出した。試料はそれぞれに対応した最終焼成温度で2時間焼結し、歯科用ダイヤモンド器具(セラムダイヤM、F、SF)にて切削し、ダイヤモンドペースト(ZirconBrite)を用いて鏡面研磨した。最終研磨終了後、アセトンで超音波洗浄した後、オートクレーブ装置にて134℃でそれぞれ5、30、60、120時間保持した。 処理後の試料をX線回折により解析しVそれぞれの試料について色彩色差計を用いて透光性を測定した。また、フィールドエミッション型走査型電子顕微鏡(FE-SEM)により微小組織の観察を行った。 Ⅲ.結果と考察 すべてのジルコニアでオートクレーブ処理時間の増加により、単斜晶含有圭の増加が認められた。また、透光性は高透光性ジルコニア、従来型ジルコニアともにほぼ変化が認められなかった。これは劣化により表面のジルコニアが正方晶から単斜晶へ変態しても、その変態層は全体の厚みから比較すると非常に薄く、また正方晶、単斜晶ともに光学的異方体であるため、結晶の変態による透光性の変化が少なかったためだと考えられた。 上記の事由から、北米においては、歯学の基礎としてのゴールド修復の重要性が再認識されてきている。先人達が築いてきた歯科医学を過去のものとするのではなく、メタルフリー材料へと応用していくことが、本学会の発展へ繋がると信じている。 オーラルリペアジェルによつて症状の改善が得られた口腔扁平苔癬の症例について○雨宮淳、斎藤道雄The Case of Applying Oral Repair Gel for providing symptomatic relief on Oral Lichen PLanus Patient Ⅰ.緒言口腔扁平苔癬は粘膜にできる角化性で炎症を伴う難治性の病変である。発症には金属アレルギー、ガルバニー電流、喫煙やストレス、C型肝炎ウイルス、薬剤アレルギーなどが発症に関わっている可能性が指摘されている。 今回、金属アレルギーによる口腔扁平苔癖が歯磨剤Oral Repair Gelによって症状が改善傾向を示したのでその効果について報告する。 Ⅰ.症例の概要 患者:57歳女性 初診:平成26年5月 現病歴:数年前より両側臼歯部頬粘膜に靡輔が生じ痛みを繰り返す。頬粘膜を動かしにくく食事摂取しにくい。 Ⅲ.治療内容 少しずつ金属Crを除去してハイプリツトに置き換える。28年5月にOralRepairGel歯磨剤使用。3か月使用して症状が軽減。 Ⅳ.材料 Oral Repair Gelは「バイオアパマタイト〇R」と乳酸菌生産物賞KSメルソ」を歯磨剤に配合し、試験管内での重金属吸着試験によりHg.Pdの吸着が認められた歯磨剤である。 考察:試験管内での吸着率はHg.Pdともに50%以上の吸着率が認められたが、試廉金属の濃度や試験管内と口腔内では条件もも異なるので経過を見ていきたい。
|
企業による多数の展示ブースが設営され、最新の歯科医療器具や情報の展示がありました。
|            
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
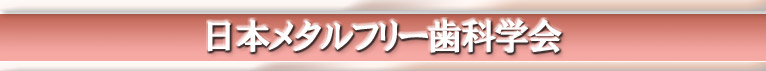

 作を伴わない光学印象採得やCAD/CAMなども日常臨床で行われるようになり、ホットな話題となっている。また、在宅高齢者の歯科治療は主に補綴治療が行われるが、種々の問題点も存在するため、どのように対応するのがベストではなくベターなのかも私見を加えたい。これらの話題や問題となっている、補綴歯科治療の今後を予測し、将来の補綴歯科治療はどのような変革をし、どのように患者に提供されるのかを考えたい。
作を伴わない光学印象採得やCAD/CAMなども日常臨床で行われるようになり、ホットな話題となっている。また、在宅高齢者の歯科治療は主に補綴治療が行われるが、種々の問題点も存在するため、どのように対応するのがベストではなくベターなのかも私見を加えたい。これらの話題や問題となっている、補綴歯科治療の今後を予測し、将来の補綴歯科治療はどのような変革をし、どのように患者に提供されるのかを考えたい。

 することが研究の最終的なゴールであり、数は多いとは言えないが、基礎研究者はそれを目標に日夜研究に励んでいる。
することが研究の最終的なゴールであり、数は多いとは言えないが、基礎研究者はそれを目標に日夜研究に励んでいる。