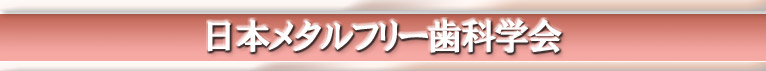|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
オールセラミックスレストレーションについて
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略 歴
|
||
| 1980年 | 東京医科歯科大学歯学部卒業 同歯科補綴学第2講座専攻生 |
|
| 1981年 | 同第2補綴科医員 | |
| 1982年 | 東京医科歯科大学大学院博士課程入学 | |
| 1986年 | 東京医科歯科大学大学院博士課程修了 同歯科補綴学第2講座医員 |
|
| 1987年 | 東京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第2講座助手 | |
| 1989年 | フンボルト財団研究奨学生としてドイツ連邦共 和国チュービンゲン大学補綴科留学 |
|
| 1999年 | 東京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第2講座教授 | |
| 2000年 | 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学分野教授 |
|
| 2001年 | 東北大学歯学部非常勤講師 | |
| 2004年 | 徳島大学歯学部非常勤(~2007.3.) | |
| 2005年 | 米国ノースカDライナ大学客員教授(~2008), 東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校 長(~2011.3.),東京工業大学非常勤講師 |
|
| 学会および社会における活動 | ||
| 日本デジタルデンテイストリー学会副会長 日本顎口腔機能学会常任理事 日本接着歯学会理事 口腔病学会理事 日本先進インプラント医療学会理事 日本補綴歯科学会,日本歯科審美学会評議員 日本補綴歯科学会専門医,日本接着歯学会認定医 |
||
ランチョンセミナー
レジン系材料による審美メタルフリー修復の可能性

山川潤一郎
株式会社トクヤマデンタル
コンポジットレジンをはじめとするレジン系材料の性能の向上は著しく、接着材の進歩とともに、審美的で耐久性に優れた修復を提供することが可能になってきている。審美性や耐久性の観点から優れていると言われるセラミック修復に対し、レジン系材料は保存的治療、メインテナンス性、即時性といった特性から、臨床上有効な選択肢の一つであり、将来さらにその適用範囲が拡大する可能性を大いに秘めている。過酷な口腔内環境においては、特にレジン本来が持つ経年劣化性の改善が課題であり、メタルフリー修復におけるレジン系材料の可能性は、機械的強度、耐久性、接着性に依るところが大きい。例えば、フィラーの粒子設計やハイブリッド化による機械的強度の向上、重合触媒の高性能化および新規接着性モノマーの開発による接着技術の向上によって、過去アマルガムや金パラが中心だった症例でもダイレクトボンディングによる修復が選択されることが一般的になってきている。また、メタルフリーを選択する大きなモチベーションの一つである審美性の観点からは、シェードラインナップの拡充だけでなく、透明性やカメレオン効果等の光学的特性の追及により、レジン系材料の中でも選択肢が広がってきている。今後、これらの技術の更なる発展によって、レジン系材料によるメタルフリー化がますます進むと考えられる。トクヤマデンタルは、球状フィラー配合コンポジットレジン「エステライト」シリーズ、高充填球状ハイブリッド型硬質レジン「パールエステ」、ジルコニアや硬質レジン等さまざまな素材の前処理材として共通に使用できる「ユニバーサルプライマー」等のこれまでの製品とともに、技術開発による新製品の展開でメタルフリー修復推進に貢献していきたいと考えている。
| 略 歴
|
||
| 1998年 | 九州大学大学院工学研究科 分子システム工学専攻卒業 |
|
| 1998年 | 株式会社トクヤマつくば研究所 | |
| 2001年 | 株式会社トクヤマデンタルつくば研究所 | |
| 2008年 | アイオウ大学歯学部客員研究員 | |
| 2009年~現在 | 株式会社トクヤマデンタルつくば研究所 | |
「ダイレクトクラウン」による新しいメタルフリー治療

高橋 純一
高橋デンタルオフィス
金属アレルギーや審美性の問題からフルメタル・クラウン(保険適用の金属使用)は昨今、患者さんから受け入れにくくなってきています。
今回、経済的理由によりセラミックやジルコニア・クラウンの施術が困難な患者さんにとって有効な「ダイレクトクラウン」(3M社製)を紹介させていただきます。
素材はコンポジットレジンで直説法を前提としていますが症例によっては間接法も選択できます。
技工料や時間の節約により患者さんには比較的安価での提供が可能です。(長期の暫間補綴と位置づけておりますので、最終的にはセラミックやジルコニア・クラウンに移行していただくよう、お話し下さい。)
今回、「ダイレクトクラウン」の術式や注意点など実際の臨床例にてお話しさせていただきたいと思います。
| 略 歴
|
||
| 1985年 | 東京歯科大学卒 | |
| 1993年 | 桃園歯科クリニック開設(東京都 中野区) | |
| 2004年 | 高橋デンタルオフィス開設(東京都 渋谷区) | |
| 2008年 | アイオウ大学歯学部客員研究員 | |
| 日本歯周病学会認定 歯周病専門医 日本臨床歯周病学会 認定医 日本歯科審美学会 認定医 日本口腔インプラント学会 認証医 |
||
シンポジウム II
審美修復におけるインプラント補綴について

塩田 真
東京医科歯科大学大学院医歯学
総合研究科インプラント・
口腔再生医学分野
インプラント治療は元来口腔の機能回復を重視する立場にあったが,近年はpatient-Centeredtreatmentの考えに基づいて、患者サイドに最も資する治療の実現を目指している。そこにはminimum invasiveの推進、治療効果のLongevityの向上 治療の安全性の保障などが含まれているが、審美性の回復も最優先課題の一つとして認識されている。
インプラント補綴は少数歯の修復による口腔内状態の改善から、多数歯の修復による顔貌に及ぶ改善まで広く審美と関わりを持っている。その実現には正常な顎位の回復のような一般補綴と共通する手法をはじめとして、インプラント埋人位置の適正化やインプラント周囲組織のconditioningといったインプラント治療に特化された手法が応用されている。とくに後者のインプラントに特化された手法はコンピュータテクノロジーの飛躍的な発展に伴うCT検査の一般化、シミュレーションソフトウェアの汎用化、CAD/CAM技術の繊細化を基幹として目覚ましい進歩を遂げている。具体的には、CTによって解剖学的状態が詳細に把握された欠損部位に対して、審美性を獲得するための適正なインプラント配置をコンピュータ上で設計し、StereOlithographで作製されたテンプレートを用いて設計された埋人位置を正確に再現することとなる。
これらと並行してインプラント上部構造に用いられる材料ならびに作製法の発展もインプラント補綴の審美性向上に大きく貢献している。インプラント上部構造には物理的強度、形態加工性、天然歯と見まがう色彩と質感などが求められる。また、万一の破折などへの方策として可撤性も備わっていることが望ましい。幸いなことにこれらはCAD/CAMで作製されたジルコニアの応用によってかなりの程度まで満たされるようになってきた。これはインプラント補綴装置が他の一般的な補綴装置と異なって、形態的に画一化されている既製品の集合体でありCAD/CAMとの相性が非常に優れていることと関連している。とりわけ粘膜貫通部が生体親和性に優れるジルコニアを用いて理想的な形態に仕上げられることは永続的な審美性の獲得にも繋がるものである。しかし、大型補綴装置の作製や校合力強度負担部位への応用に際してジルコニアはまだ問題を残している。同様な材料としてニケイ酸リチウムも用いられているが問題の解決には及んでいない。ハイブリッドセラミックスも理想的な材料とは程遠い位置にあるといってもよいだろう。今回の講演では、インプラント審美補綴の現状を解説するとともに、今後の課題についての考察を試みたい。
| 略 歴
|
||
| 昭和55年3月 | 東京医科歯科大学歯学部卒業 | |
| 昭和55年4月 | 東京医科歯科大学大学院歯学研究科 博士課程入学 |
|
| 昭和59年3月 | 東京医科歯科大学大学院歯学研究科 博士課程修了 |
|
| 昭和59年4月 | 東京医科歯科大学歯学部附属病院 第二補綴科医員 |
|
| 昭和63年4月 | 東京医科歯科大学歯科補綴学第二講座助手 | |
| 平成 8年3月 | 文部省在外研究員ジュネーブ大学出張 | |
| 平成 8年9月 | 東京医科歯科大学歯学部附属病院 インプラント治療部助教授 |
|
| 平成12年4月 | 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 インプラント学助教授 |
|
| 日本口腔インプラント学会評議員 WC01評議員 現 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 インプラント学准教授 |
||
メタルフリー歯科時代におけるインプラント

本間 憲章
(医)本間歯科院長
現在はチタンインプラントが主流となっているが、それに至るまで様々な材料・システムが研究開発されてきた。20世紀にはCo-Cr-Mo合金(バイタリウム)が発明されインプラント材料として用いられ、その後ブローネマルクにより発見されたオッセオインテグレーションの獲得や生体親和性に非常に優れた金属であるという点からチタンインプラントが主流として多く用いられてきた。
そして近年、金属にかわる材料としてセラミックス材料であるジルコニアによるインプラントの研究開発が進められ、既に欧米では臨床においても多く使用されるようになってきている。
チタンは生体親和性に非常に優れ、また不動態膜を形成し口腔内においても非常に安定な金属であるため、金属アレルギーを引き起こすことはまず無いと言われてきた。しかし現在、チタンは多くの製品で使われるようになり、人々がチタンに触れる機会が増えることで感作され、チタンによる金属アレルギーが起こる可能性もゼロとは言い切れないのが現実であり、既にそのような症例報告もされている。
歯科金属アレルギーの問題が多く世間で取り上げられ人々の間でも口腔内への関心が高まっている現在、金属アレルギーを持つ人や可能性のある人に対しては、その不安を少しでも軽減するためにメタルフリー歯科治療を推進・提供すべきであり、インプラントもその例外ではない時代になりつつあると感ずる。
現在チタンと同様にオッセオインテグレーションを獲得する非金属のインプラント材料としてはジルコニアがある。欧米では数社からジルコニアインプラントが発売されており、その中でもスイスのZ-Systems社のジルコニアインプラントは、EUならびにFDAの認可を受けている。この10年で28000本以上の埋人件数があり、1年生存率は99%、そして7年の残存率も95%と確かな科学的証拠・臨床成績を示している。
歯科金属アレルギーが問題となっている近年、インプラント治療における選択肢の一つとしてジルコニアインプラントを提示出来る様にしていくべきではないだろうか。今後、術前の金属アレルギー検査、特にチタンアレルギー検査が行われる様になれば、益々その必要性は増加するに違いない。
私は2009年2月にこのZ-Systems社製のジルコニアインプラント埋入手術を行い、その後も同社により改良され欧米で販売されている製品も使用して、ほぼ満足する結果を得ているので、紹介したい。
| 略 歴
|
||
| 日本歯科大学 卒業 東京女子医科大学病院歯科口腔外科入局 村瀬正雄教授 河西一秀教授に師事 東邦医科大学医学部薬理学教室特別研究員 伊藤隆太教授に師事 米国 University of Michigan 留学 渡加 McGill University・Montreal General Hospital 勤務 帰国後 干葉市内開業 現在医療法人本間歯科理事長・医療法人干寿会理事 |
||
| lCOl国際インプラント学会 アジア太平洋地区認定医審査委員 日本顎顔面インプラント学会 運営審議委員 国際歯科学士会 Fellow 暁星歯学会会長 日本歯科大学 非常勤講師・臨床講師 医学博士 |
||
皮膚科医からみた歯科金属アレルギーの現状

海老原 全
慶應義塾大学医学部皮膚科
皮膚科医が一般に接する金属アレルギーは接触皮膚炎である。接触皮膚炎は外来性の物質が皮膚に接触して生じる皮膚の炎症であり、外界物質に対する生体異物排除機構に伴い形成されるものである。そのため、生活環境などと密接な関係があり、時代により、新たな接触アレルゲンが出現するなど、原因物質についても変遷があり、診療側としてはその動向を知っておく必要がある。
日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会は接触アレルゲンの動向を発表してきたが、最近の報告でも上位を金属が占めることについては変わらず、相変わらず金属は接触アレルギーをおこしやすい物質の代表である。しかし、日本では社会的にまだまだその認識は低く、金属製品は増加するばかりで、金属アレルギー対策、感作予防については啓蒙されているとは言いがたい。今後も金属アレルギーについては減少することはないと予想され、金属アレルギーの動向について、歯科医師,医師は十分に知っておく必要があると考えられる。
今回の発表では金属アレルギーによる皮膚症状について概説し、近年の金属アレルギーの考え方に触れ、歯科金属アレルギーの傾向、金属アレルゲンの傾向について述べる。
| 略 歴
|
||
| 1986年 | 慶應義塾大学医学部 卒業 | |
| 1986年 | 慶應義塾大学医学部皮膚科学教室入室 国立小児病院,清水市立清水総合病院, 東京電力病院 出向を経て |
|
| 1993年 | 慶應義塾大学病院診療科医長(皮膚科外来担当) | |
| 1996年 | 東京都済生会中央病院皮膚科医長 慶應義塾大学兼任講師(医学部皮膚科学 |
|
| 2005年 | 慶應義塾大学専任講師(医学部皮膚科学) | |
| 2010年 | 慶應義塾大学准教授(医学部皮膚科学) | |
特別講演
歯科材料アレルギーを考慮した治療法のあり方

松村 光明
東京医科歯科大学歯学部附属病院
歯科アレルギー外来
19世紀から20世紀にかけて、精密鋳造法の確立と高速切削法の開発、高性能印象材の出現により、それまでのバンドクラウンから間接法によるフルキヤストクラウンが主流となり、近年ではフルキヤストクラウンやメタルセラミックスクラウンからオールセラミックスクラウンヘと、歯科界も“21世紀のパラダイムシフト”と呼ぶべき大きな転換期を迎えています。歯冠修復材科のみならず、欠損補綴材料として歯科医療分野では従来から、金属が広く用いられています。金属材科は適合性、強度など非常に優れた物性を有しており、適応範囲が広く、長期予後に優れ、現在なお歯科医療の現場においては非常に重要な役割を担っていますが、一方で歯肉や歯根の変色、歯根破折、金属アレルギーなどが問題視されています。口腔内にて溶出した金属や、食品中に微量に含有される金属成分が経口、経気道的に摂取され、血流に乗り様々な部位にアレルギー症状を引き起こします。アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎、掌既膿病症、扇平苔癖、難治性痺疹といった疾患が全身性に生じ、その悪化因子として金属アレルギーが示唆される報告が多く見られるようになっています。
歯科医療の範囲に留まらず、医療界においては整形外科領域や血管外科領域では人工生体材料としてステンレス製の血管拡張用バルーンやTi合金製の動脈癌クリップ、純Ti、Ti合金及びCo-Cr合金を併用した人工股関節などが生体に用いられます。歯科領域ではチタン系金属材料を用いたインプラントや外科手術後の固定用金属プレートは、使用中に不具合を生じなければ半永久的に生体内に留置されることになります。現在、医療分野にて多用されている金属材料によるアレルギーの発症率は決して高くはなく、発症率数%の疾患に対してスクリーニング検査を実施する必要性を疑問視する医療関係者もいますが、歯科材料アレルギーを、安全であると考えられていた治療法及びその使用材料に起因する思わぬ医原性の合併症として捉えるのであれば、適切な検査法を用いて、アレルギーの診断がなされてしかるべきと考えます。東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科アレルギー外来では歯科に限らない各医療分野からの依頼を受け、金属パッチテストや、現代セラミックス治療では必須となったレジン系高分子複合材料のアレルギー検査や、リンパ球刺激試験(血液検査)、口腔内金属成分分析検査などのアレルギー検査をもとに総括的診断を行なっています。
本講演では「歯科材料アレルギーを考慮した治療法のあり方」と題し、歯科用金属やセメント、レジン、根管治療材料など、多岐に渡る歯科材料アレルギートラブルについて、その症状、診査・診断、検査方法、最先端のメタルフリー・トリートメントに、身体への優しさを加えたアレルゲンフリー・トリートメントのあり方を皆様と共に考えたいと思っております。
| 略 歴
|
||
| 東京医科歯科大学歯学部附属病院 歯科アレルギー外来 臨床教授 医療法人社団優恒会 松村歯科医院 理事長/院長(東京医科歯科大学 臨床研修施設指定) |
||
| 1980年 | 東京医科歯科大学歯学部卒業同第2歯科補綴学教室入局 | |
| 1987年 | 同第2歯科補綴学大学院卒業 | |
| 1990年 | 医療法人社団優恒会松村歯科医院開設(世田谷区) 東京医科歯科大学第2歯科補綴学教室非常勤講師 |
|
| 1997年 | 日本歯科補綴学会認定医・指導医 | |
| 1999年 | 東京医科歯科大学歯学部歯科アレルギー外来臨床教授 | |

会場には展示ブースが設営され、最新の歯科医療器具や情報・書籍等の展示がありました。









| 協賛団体・企業様 | |
| ■ 株式会社ジーシー | ■ クラレノリタケデンタル株式会社 |
| ■ ブラウン オーラルB プロクター&ギャンブル・ジャパン株式会社 | |
| ■ ペントロンジャパン株式会社 | ■ シロナデンタルシステムズ㈱ |
| ■ 株式会社スマートプラクティスジャパン | ■ ストローマン・ジャパン株式会社 |
| ■ Z-Systems Japan | ■ 株式会社 ヨシダ |
| ■ 株式会社 杏友会 | ■ 株式会社松風 |
| ■ 株式会社トクヤマデンタル | ■ 相田化学工業株式会社 |
| ■ スリーエムヘルスケア㈱ | |
| 日本メタルフリー歯科学会 2013 |